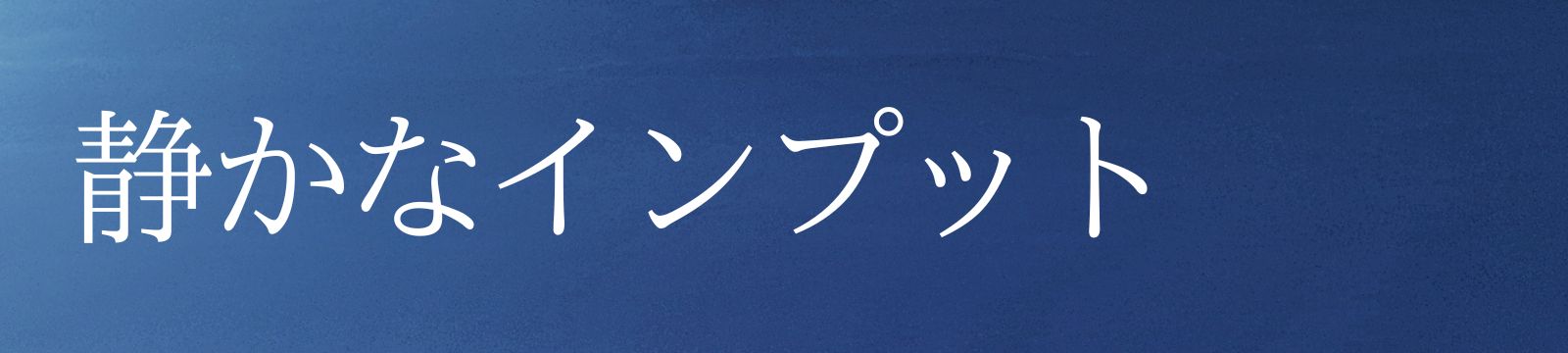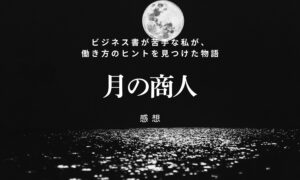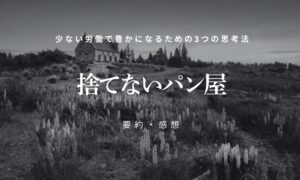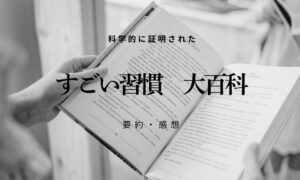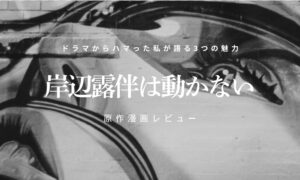はじめに|“借り物の知識”では語れないものがある
『乱読のセレンディピティ』を読んで、いちばん深く心に残ったのは、
「知識はすべて借り物である」という言葉だった。
本をたくさん読んで、いろんなことを知っているように見えても、
それが“本当に自分のもの”になっているかはまた別の話。
知識はあくまで借り物で、
それを時間をかけて自分の中に沈め、
自分の言葉として話せるまで熟成させる過程が必要なんだと感じた。

乱読のセレンディピティ【文庫電子版】 (扶桑社BOOKS文庫)
思考と読書|誰かの言葉で話す人に感じる違和感
この感覚は、読書だけでなく、日々の会話にも通じる。
たとえば職場やSNSで、どこかで聞いたような言い回しを、
そのまま“自分の意見”として話す人に出会うと、
「それって本当に、あなたの言葉?」と思うことがある。
でもそれは、過去の自分にも思い当たること。
誰かの考えをそのまま借りて、あたかも自分の声のように話していた頃のこと。
だからこそ今は、
本から得たことも、一度自分の中で噛み砕いてから言葉にしたいと思っている。
やみくもに読むからこそ、ひらめきが宿る
この本の中で特に共感したのが、
「本はやみくもに読むのがよい」という考え方だった。
偶然手に取った1冊や、流れで読み始めた本のなかに、
自分だけの発見がある。
知識を整然と並べるような読み方よりも、
思いがけない出会いのほうが、記憶に残ることがある。
読書に「意味」や「効率」を求めすぎていた自分にとって、
この感覚はほっとするものだった。
忘れることを、こわがらなくていい
もうひとつ印象に残っているのが、「忘却のすすめ」。
“本は読んだら忘れるにまかせるのが一番よい”
最初は少し戸惑ったけれど、今ではこの考え方がすごく好きだ。
忘れてしまうことは、失うことではない。
むしろ、心に馴染んだものだけが自然と残っていく。
そして必要なときには、ふとよみがえる。
それはただの記憶ではなく、
自分の中で成熟した思考として戻ってくる感覚。
自分の読み方を、少しずつ取り戻していく
著者の外山滋比古さんの本は、以前『思考の整理学』で出会った。
あの本も好きだったけれど、
この『乱読のセレンディピティ』のほうが、今のわたしにはしっくりきた。
似た内容もあるけれど、それでもまた読みたくなる。
違う季節に、同じ景色を見るような感じ。
その時々の自分が求めていた言葉に、そっと出会える本。
おわりに|読むことは、自分の言葉を育てること
わたしはこれからも、
おそらく“思考を耕す”ために本を読むんだと思う。
読んで、忘れて、
でも、ふとした瞬間に思い出して、
それを自分の言葉で話せるようになるまで。
読むという行為が、
生活の中に静かに混ざっていることの豊かさを、
この本はあらためて思い出させてくれた。
きっとまた、なんでもない日の午後に、そっと開きたくなる。
そんな風にそばにいてくれる1冊。
🛒 本はこちらからどうぞ
「ちゃんと読まなきゃ」と思っていた人にこそ、
本ともっと自然につきあえる感覚をくれる一冊です。