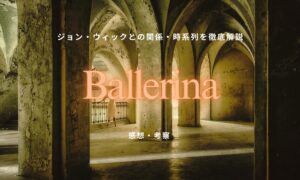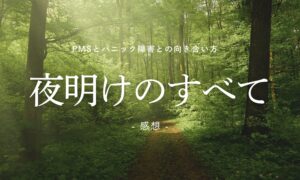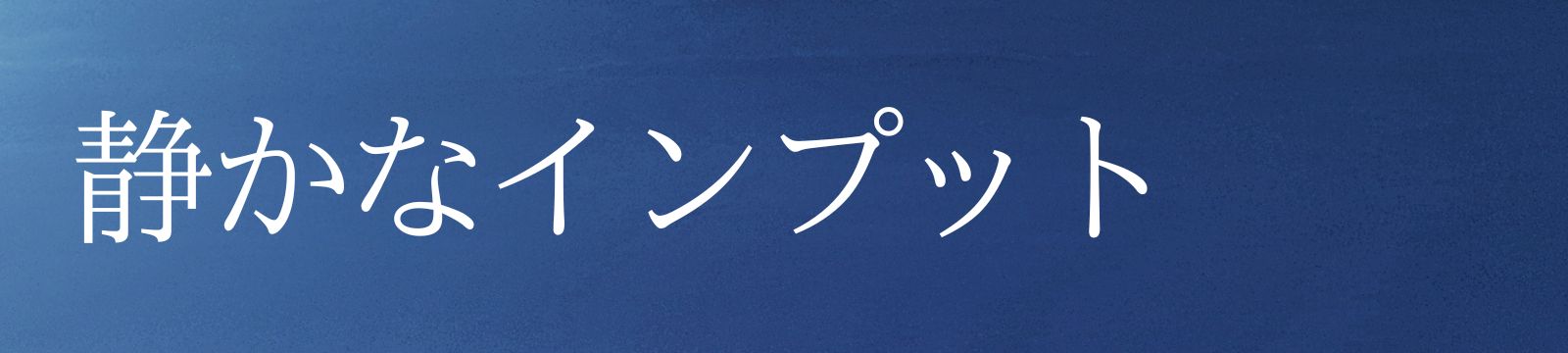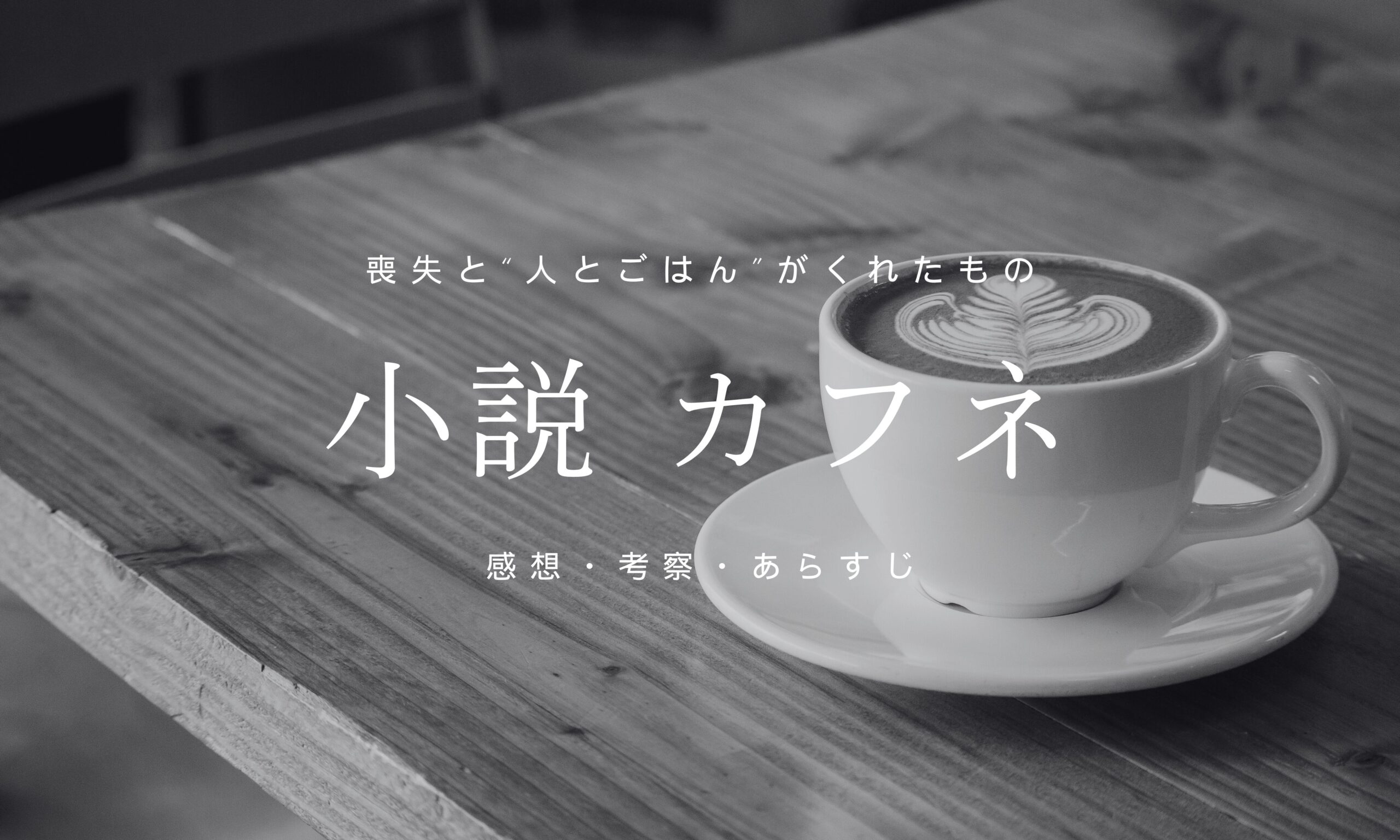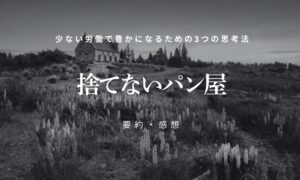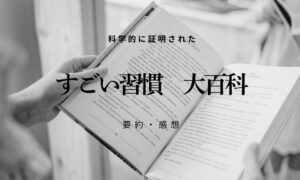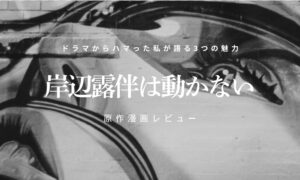静かに心を撫でる小説。
愛する人を失ったふたりが、「食べること」で繋がっていく日々。
小説『カフネ』の感想・考察・あらすじをまとめました。
『カフネ』が心に残る理由(感想)
この物語を読み終えたあと、しばらくのあいだページを閉じられなかった。
誰かを失うということ、その痛みの中でなお、人と出会ってしまうこと。
そして「食べる」という何気ない営みが、どれほど深く、そっと人の心に触れるものかを思い知らされる。
『カフネ』は、
感情を大声で語らない。だけど確実に、感情の奥へと静かに降りていく物語だった。
『カフネ』あらすじ(ネタバレなし)
法務局で働く野宮薫子は、弟・春彦を突然の死で失い、悲しみに閉じ込められていた。
ある日、春彦の遺言書から浮かび上がった名前——小野寺せつな。
弟の元恋人だった彼女と出会い、やがてせつなが勤める家事代行サービス「カフネ」の仕事を手伝うことになる。
かつて同じ人を大切にしていたふたり。
最初はぎこちなく、どこかよそよそしい。
けれど、“食べること”を通して、少しずつ心が動きはじめる。

『カフネ』感想|「誰かと食べる」ことの静かな力
料理を一緒に作る。
一緒に食べる。
ただそれだけの行為なのに、ふたりの間にある沈黙が、すこしずつ変わっていく。
この作品では、“ごはん”がどこまでも静かで、それでいてどこまでも強い。
- 誰かに食べてもらうために用意する
- 相手の好みに合わせる
- それが、ひとつの感情表現になる
そうしたことに、改めてハッとさせられた。
『カフネ』考察|タイトルの意味と物語のやさしさ
“カフネ(cafuné)”とは、ポルトガル語で
「愛する人の髪にそっと指を通すしぐさ」を意味する。
この言葉の選び方が、本当に美しい。
薫子とせつなは、傷ついた心をむりに癒そうとするわけじゃない。
むしろ、お互いの過去に踏み込みすぎない距離感を保っている。
だけどその距離感のなかで、“暮らしを分かち合う”というやさしいつながりが生まれていく。
それはまさに、言葉にしない「カフネ」なのだと思う。
わたしにとっての“静かなインプット”
この小説に出てくる人たちは、どこか「人との距離」を考えながら生きている。
それは優しさでもあり、恐れでもあり、そして――覚悟だ。
わたし自身、似たような状況を経験したからこそ、
薫子がどうやって人と向き合うのか、そのプロセスに自然と引き込まれた。
周囲の人たちとの関係の築き方も、決して表面的な“仲の良さ”ではない。
それぞれが、自分の傷を抱えたまま、真の関係に向き合おうとしている。
真の関係は、「仲が良い」だけじゃ築けない。
自分を見せること、相手を知ろうとすること。
それには、静かな覚悟がいるのだと思った。
この本を、あの人に渡すとしたら
この物語は、
大切な人を失った経験のある人には、きっと深く届くと思う。
でもそれだけじゃない。
今、何かに耐えている人。
日々の中で苦しさを抱えている人。
そういう人が読んだとき、
「あ、わたしは一人じゃないかもしれない」って、ふと思えるような本なんじゃないかと思った。
おわりに
大きな感動も、劇的な展開もないけれど、
『カフネ』は感情の奥を静かに撫でるような、あたたかい物語だった。
あなたの暮らしの中にも、そっと寄り添ってくれるページがきっとあると思う。
大きな感動も、劇的な展開もないけれど、 『カフネ』は感情の奥を静かに撫でるような、あたたかい物語だった。
あなたの暮らしの中にも、そっと寄り添ってくれるページがきっとあると思う。
この優しい物語を、あなたの本棚にも加えてみませんか?
普段 Amazon を使っている方はこちらから、サクッと電子書籍(Kindle)で読むのがおすすめです。 👉 Amazon Kindle版→ カフネ
楽天ポイント を貯めている、または紙の本でじっくり世界観に浸りたい方はこちらをどうぞ。 👉楽天ブックス→ カフネ [ 阿部 暁子 ]