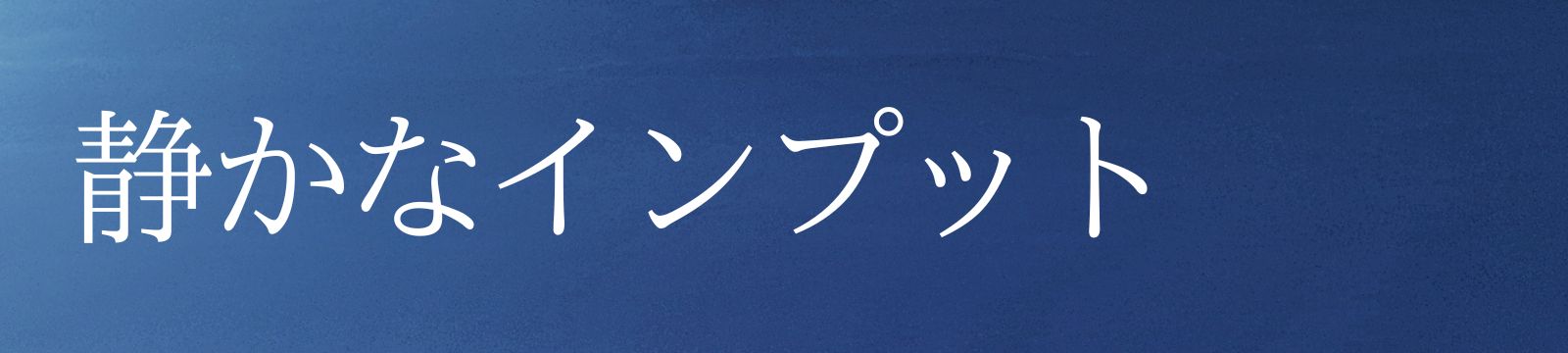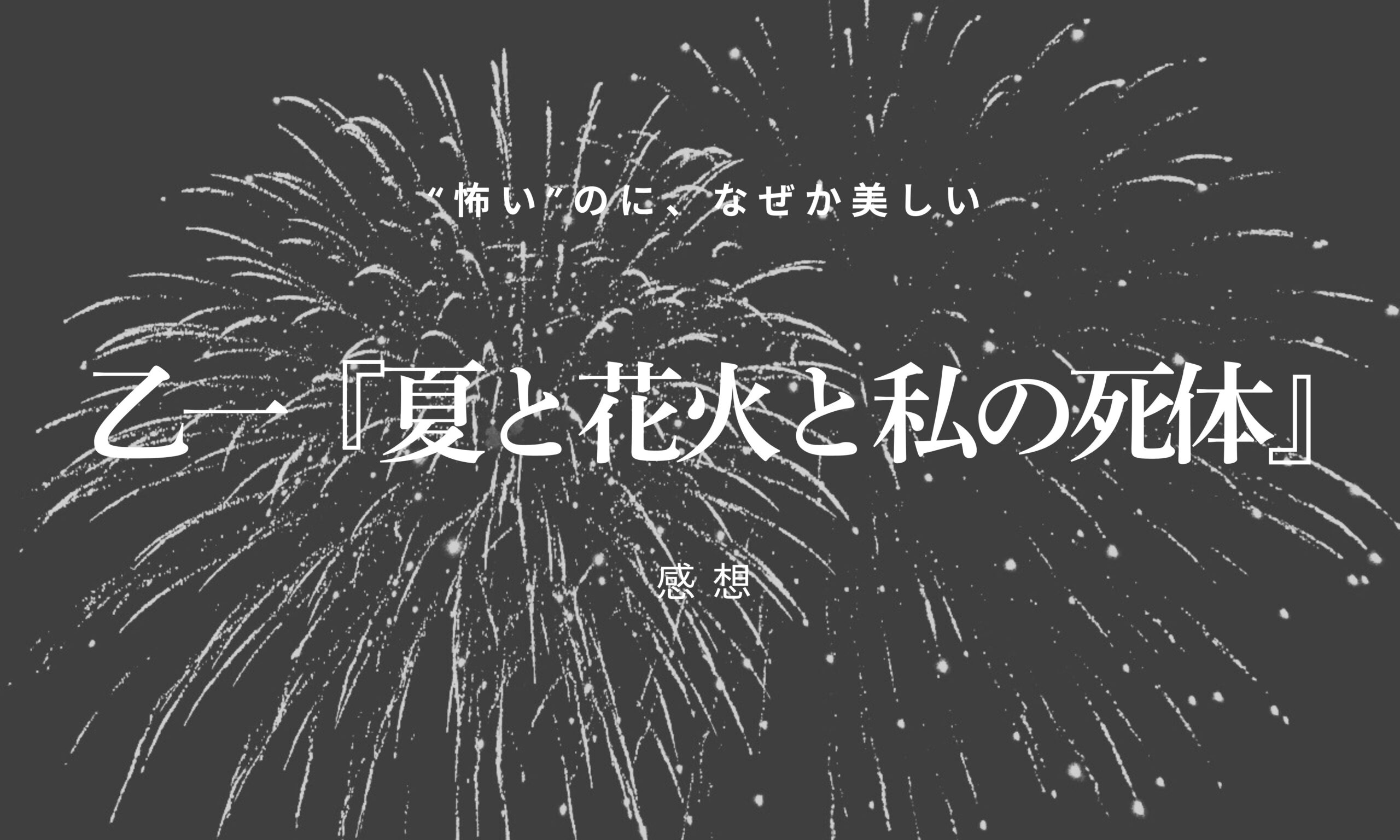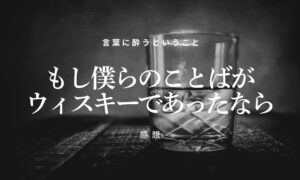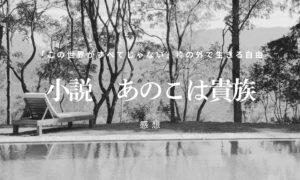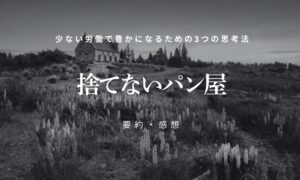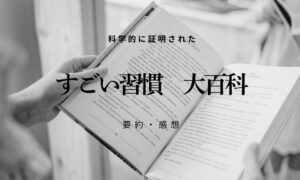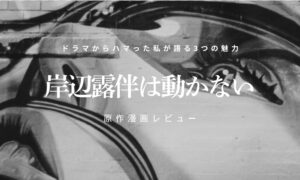📘 簡単なあらすじ(乙一『夏と花火と私の死体』)
9歳の夏、私は死んだ。
でもこの物語は、そこで終わらない。
語り手は、すでに“死体”になった少女。
彼女の視点から、ひと夏の出来事が淡々と語られていく――
自分の死を引き起こした人たちの行動、
その場をどう取り繕うか、隠し通そうとする子どもたちの葛藤。
ただのホラーではなく、
子どもの無邪気さと残酷さが、美しさをまとって描かれる物語。
“死”というテーマのはずなのに、なぜか冷静で、
どこか澄んだ空気すら感じさせる語り口。
読むたびに、「怖いってなんだろう」「人間らしさってなんだろう」
そんな問いが、じわじわと心の奥に残る一冊です。

夏と花火と私の死体 (集英社文庫)
夏になると、もう一度読みたくなる本
毎年、夏になるとふと思い出す。
『夏と花火と私の死体』――
タイトルの中にある“死体”という言葉の異質さと、
“夏”や“花火”という、どこか懐かしくて甘い響きとのコントラスト。
この作品を初めて読んだときの感覚が、いまでもまるごと蘇ってくる。
私が乙一を知ったのは、この一冊がきっかけだった。
そこから『ZOO』や『失われる物語』も読んでみたけれど、
やっぱり最初に出会ったこの物語の印象が、いちばん強く残っている。
ただ怖いだけじゃない。
むしろ、こわさの奥にある冷たさを感じるけど、それが心地よくすらあるような感覚とか、
子どもの無邪気さゆえの残酷さとか――
そんな感情に、私は何かを強く揺さぶられた。
語り手が“死体のわたし”という不思議な距離感
語り手が「死体のわたし」である、という設定にも最初は戸惑った。
死んでしまったはずの“私”が、冷静に状況を語っていく。
それは怖いというよりも、不思議で――
どこか、世界から少し切り離された場所から眺めているような感覚だった。
生きている人たちの慌ただしさや、感情のぶつかり合いを、
ひとつひとつ観察するような口調で描かれていく。
怒りや憎しみといった強い感情ではなく、
どこか温度のない、乾いた目線で物語は進んでいく。
むしろ怖かったのは、残された人たちのほうだった。
子どもだからこその判断の甘さや、
隠したい、守りたい、バレたくない――
そんな気持ちが入り混じった行動のほうが、
読んでいてじわじわと緊張を生んでいった。
死体になった「私」は何もできない。
ただ、見ているだけ。
でもその“見ている”という在り方が、
読者の心を離さないような、妙な存在感を放っていた。
気がついたら怖かった。無自覚な残酷さと子どもの美しさ
怖い物語なのに、読んでいる最中はどこか落ち着いていて、
「うわ、こわい…!」と叫びたくなるようなシーンはない。
なのに、ページを閉じたあとで、ふと気づく。
これは、たしかに“怖い話”だった。
でもその怖さは、よくあるホラーとはまったく違っていた。
びっくりさせたり、音で煽ったりするようなものじゃなくて、
語りの淡々とした調子の中に、じわじわと滲み出す不穏さがある。
それに、どこか距離のある語り口。
死体の“私”という設定だからこその、客観的で温度のない視点。
その距離感が、むしろ読み手の想像を引き出して、
より強く心に残るのかもしれない。
小学生たちの純粋さも印象的だった。
まっすぐで、疑うことを知らない子どもたち。
でもその無垢さゆえに、大人とは違う怖さが生まれていた。
善悪では測れない、あの判断と行動の裏側にある、
「無自覚な残酷さ」と、それを正当化しない物語の姿勢が、美しさにすら感じられた。
この作品が、なぜずっと心に残っているのか
きっとこの物語が忘れられないのは、
“死”や“こわさ”を描いているのに、
どこか感情を静かに受け止めてくれるような、そういう余白があるからだと思う。
わかりやすいメッセージがあるわけでもない。
泣かせようとする演出も、感動させようとする言葉もない。
それでも、読み終えたあとに何かが残る。
もしかしたら私は、子どもの無垢な世界の裏にある“怖さと美しさの共存”に、
ずっと惹かれているのかもしれない。
毎年夏になると、あの感覚を思い出す。
そしてもう一度、ページをめくりたくなる。
The scariest truths are told by those who don’t mean to scare.
(本当に怖い真実は、怖がらせるつもりのない人から語られる。)
物理書籍リンク(楽天ブックス)↓

電子版リンク (Kindle版 on Amazon)↓