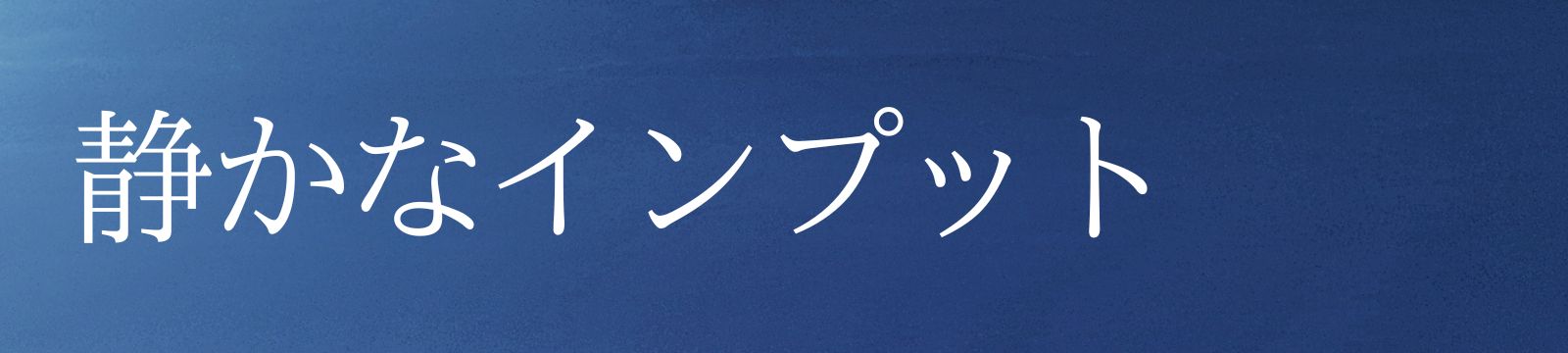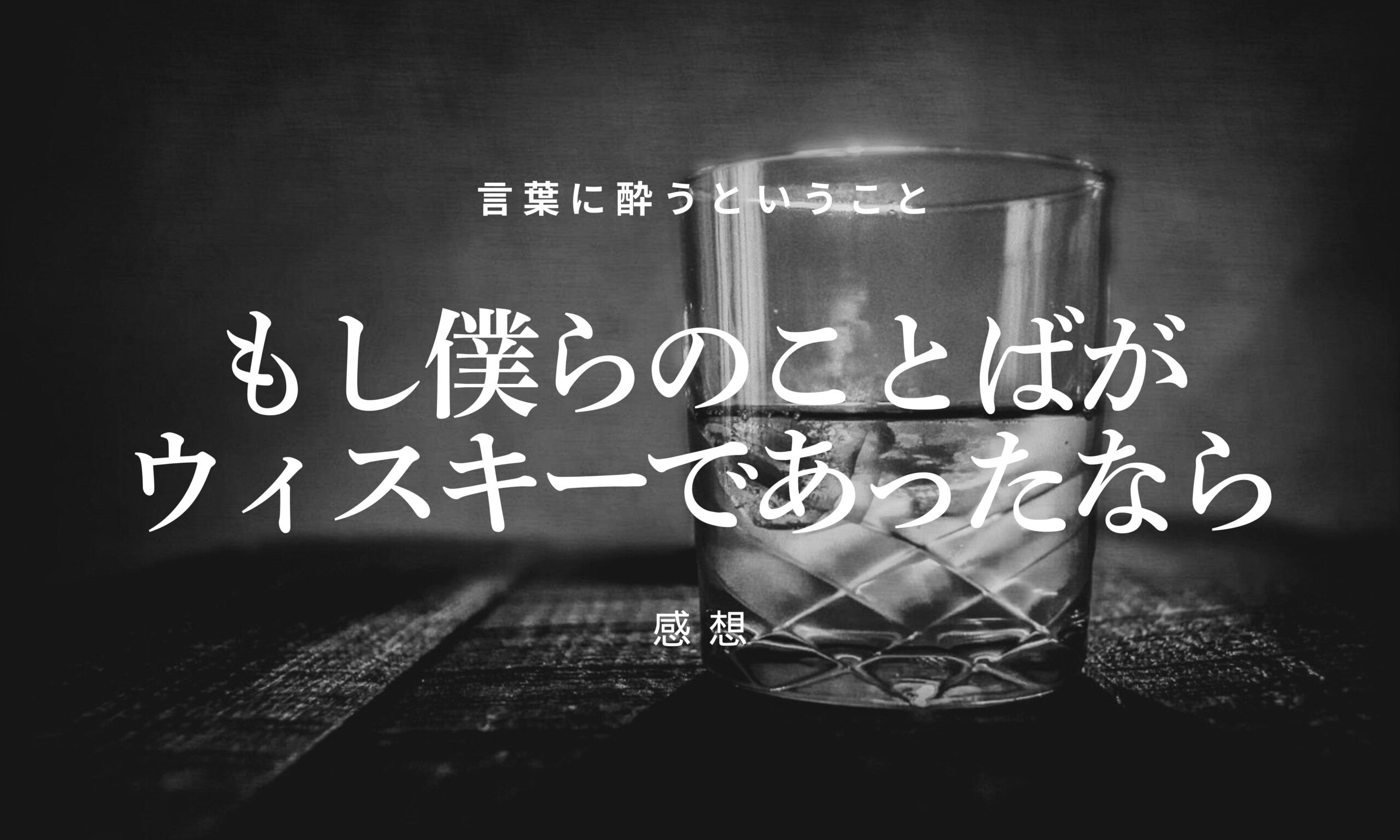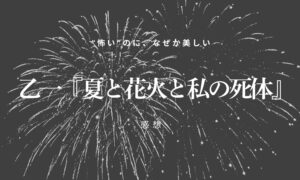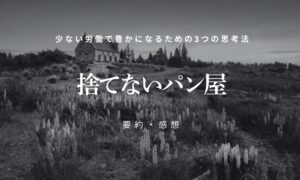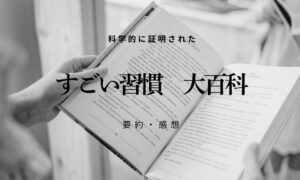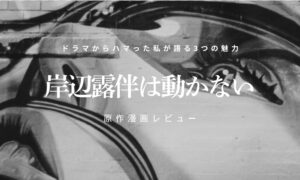目次
1|はじめて読んだ村上春樹は、この旅エッセイだった
実を言うと、私はずっと村上春樹を読まずにいた。
なんとなく、まわりに熱烈なファンが多くて、「信者」みたいな空気がちょっと苦手だった。
本屋でもずっと平積みにされてるし、名作扱いされすぎてて、逆にどこから入ればいいのかわからない。
近づきにくさがあった。触れたら最後、深みにハマるような感じ。
映画で言うなら、岩井俊二みたいな存在。世界観が濃くて、美しくて、でも今じゃない気がして、距離をとってしまっていた。
そんな私が初めて読んだのが、この『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』。
理由は単純で、タイトルに惹かれたからだった。
なんて、いいタイトルなんだろうと思った。
読みもせずにずっと避けてきたくせに、この言葉の並びにだけは抗えなかった。
詩みたいだなと思った。落ち着いていて、余韻があって、あたたかくて、どこか寂しい。
そういうタイトルをつける人の文章なら、読んでみたいと思った。

もし僕らのことばがウィスキーであったなら(新潮文庫)
2|お酒が飲めない私が、ウィスキーに酔ったような気がした
私はお酒がまったく飲めない。
アルコールアレルギーで、ワインも、ビールも、ウィスキーも、一滴もダメ。
だから正直、ウィスキーの味も香りも知らない。飲んだことがない。
それなのに、この本を読んでいる間ずっと、酔ったような感覚があった。
スコットランドのアイラ島、それからアイルランド
土地の空気、静かな蒸留所、ガラス越しに揺れる琥珀色の液体。
ひとつひとつが、まるで音楽を聴くように、穏やかに体の中に沁みてきた。
ウィスキーって、きっと言葉と似てるのかもしれないと思った。
時間をかけて、蒸留されて、寝かされて。
すぐには伝わらないけど、深く伝わるもの。
そういう言葉が好きだと思った。
この本には、そういう言葉が、ぽつぽつと並んでいた。
強く語らないのに、やさしく心に残るような。
それがなんだか、心地よかった。