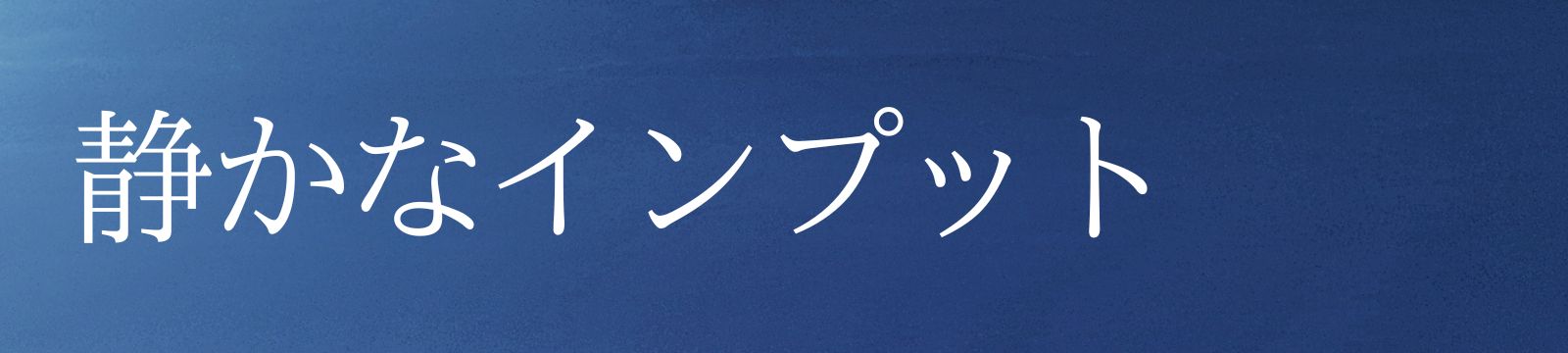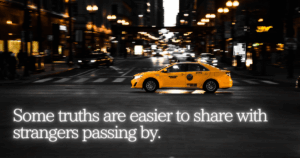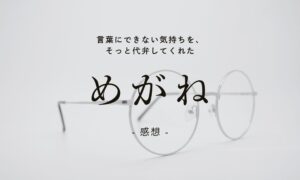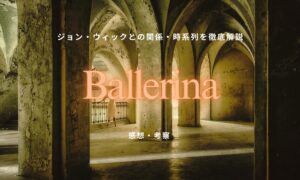「誘拐した少女は、ヴァンパイアだった」
この映画のあらすじは、とてもシンプルです。しかし、物語が進むにつれて、私はある奇妙な感覚に囚われました。
それは、少女の姿をした怪物アビゲイルへの「恐怖」ではなく、むしろ彼女の心の奥底にある、計り知れないほどの「退屈」に対する、物悲しい共感でした。
この記事は、単なるサバイバルホラーのレビューではありません。
100年以上の時を生きる怪物が本当に求めていたものは何だったのか、その魂の飢えについて、深く考察していきます。
※この記事は、映画『アビゲイル』の結末や核心に触れるネタバレを含みます。未鑑賞の方はご注意ください。
目次
作品情報:ホラーの名手たちが仕掛ける、新たな恐怖
本作の監督は、『スクリーム』シリーズや『レディ・オア・ノット』で知られる制作会社レディオ・サイレンスのマット・ベティネッリ=オルピンとタイラー・ジレット。主演には『イン・ザ・ハイツ』のメリッサ・バレラや、『ザ・スイッチ』のキャスリン・ニュートンなど、新世代のホラークイーンたちが集結。
この布陣だけでも、ただのホラーで終わらない、一筋縄ではいかない物語であることが伺えます。