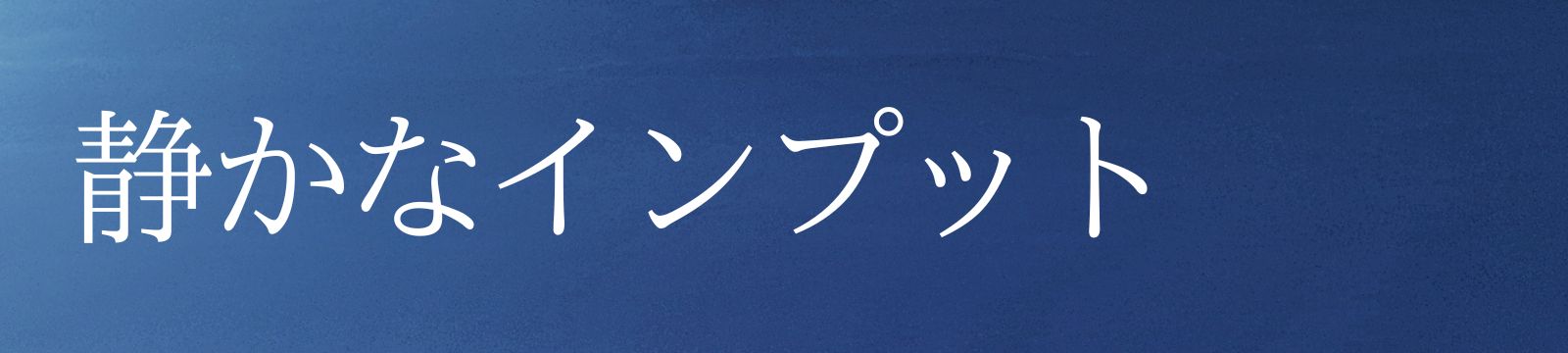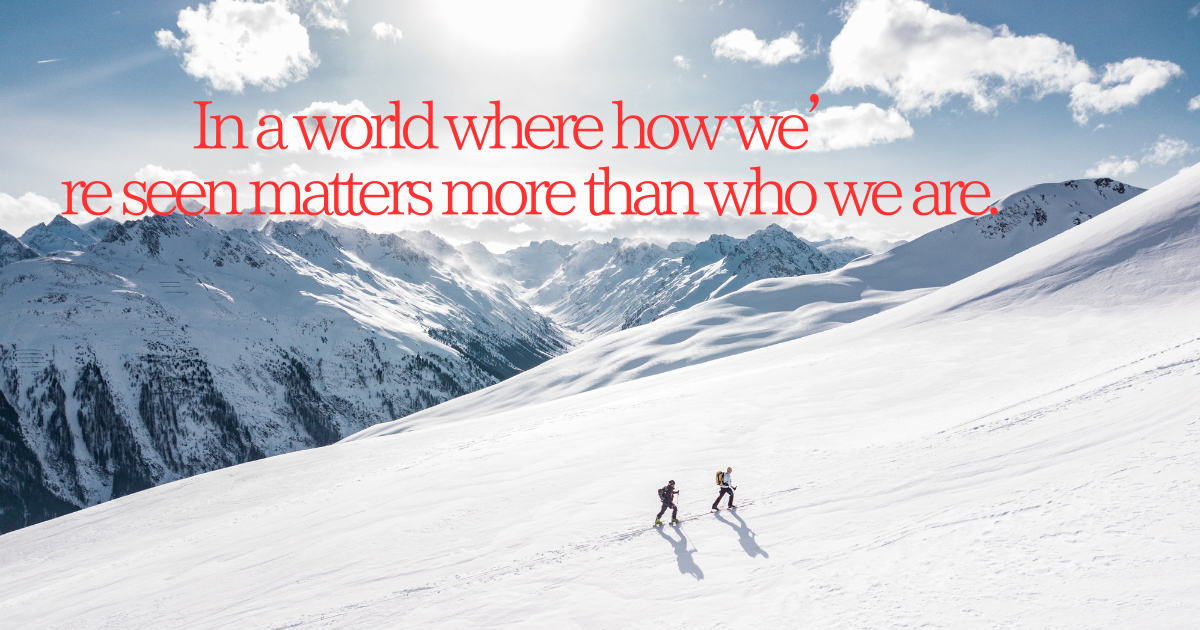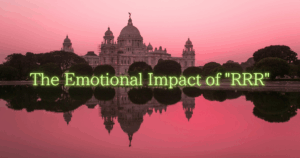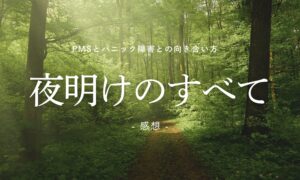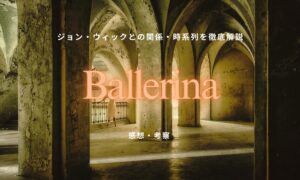映画館に貼られていたポスター。
そのビジュアルを見た瞬間、「これ、きっと好きなやつだ」と思って、
何の前情報もなく、観に行ったのが『落下の解剖学』だった。
観終わったあと、言葉にならないモヤモヤがずっと残った。
「真実は何だったのか」ではなく、
「人は何を信じたいのか」で物語が動いていく感じ。
その構造が、この世界そのもののように思えた。

落下の解剖学(字幕/吹替)
目次
「どう見えるかが大事だ」
作中で、弁護士が言う。
「真実じゃなくて、どう見えるかが大事だ」と。
それを聞いたとき、
ああ、これは映画の中の話だけじゃないなと思った。
裁判はもちろん、
会社でも、学校でも、SNSでも、
わたしたちはいつも“どう見えるか”で人を判断している。
もっと言えば、“どう見られるか”を操作できる人が、
生きやすくなっていく構造が、もう社会全体にしみついてる。