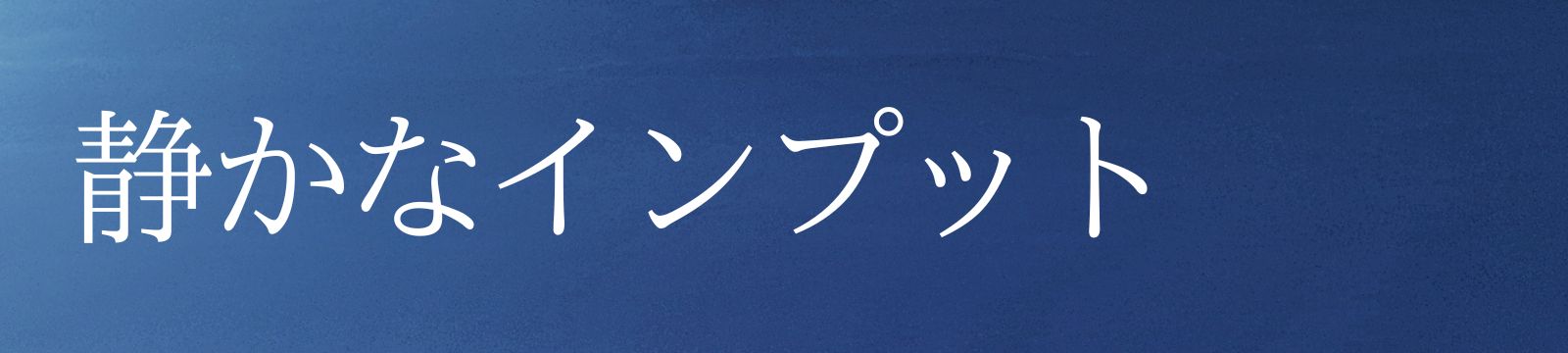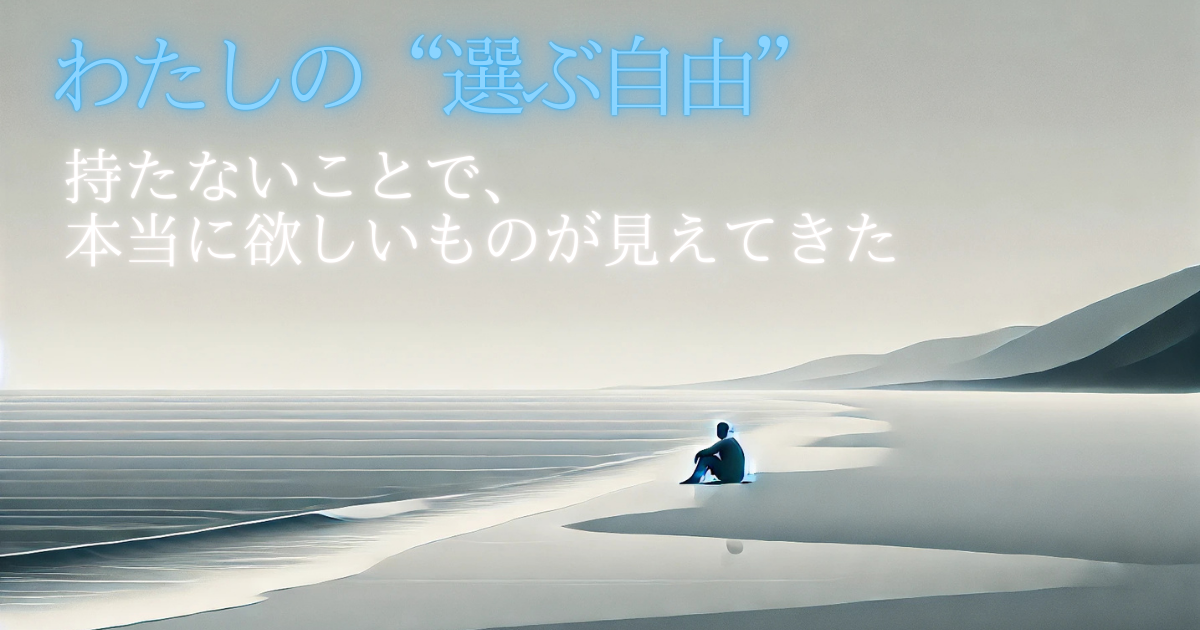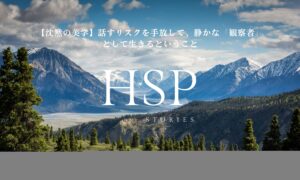はじめに|選ぶ、ということの静かな強さ
わたしは“選ぶこと”が好きだ。
それは「多くの中から選ぶ」ことではなくて、
「本当に自分に合うものを、ちゃんと見つけて選ぶ」こと。
いつの間にか、私たちの暮らしは“選ばされる”場面であふれている。
情報も、人間関係も、モノも。
けれど、そこであえて立ち止まって、「選ばない」ではなく「選ぶ」ことに集中してみる。
その自由が、思っていた以上に心を心地よく整えてくれた。
テレビをやめたら、音が澄んで聴こえた
去年、引っ越しを機にテレビを置かない生活を始めた。
深い理由があったわけじゃない。ただ、ふと「なくてもいいかも」と思った。
それまでは、帰宅してすぐテレビをつけるのが当たり前だった。
BGMのように流れてくる音。
けれど今、部屋の中にあるのは自分で選んだ“音”だけになった。
聴かされるのではなく、聴くという行為を自分の手に戻せたことが心地よかった。
音楽もそう。
その日の気分に合うものをじっくり選んで流す時間が、
なんでもない夜をすこしだけ特別にしてくれる。
「便利」から距離を置いて、見えたこと
電子レンジも今の生活にはない。
最初は少し不便かな?と思っていたけれど、
火で温めたり、冷たいままでも意外と平気だった。
むしろ、手間をかけることのやさしさに気づいた。
温めなおすことが、食べものと向き合い直す時間になった。
「あると便利」なものってたくさんある。
でも、“本当に必要かどうか”は別の話。
便利さの手前にある時間や感覚のほうが、わたしにとっては大切だったりする。
わたしが選ぶのは、“感性が喜ぶ”もの
家電ひとつを選ぶのにも、時間をかける。
デザイン、機能、価格――全部ちゃんと調べる。
「とりあえず」で選びたくない。
暮らしに置くものは、自分の感性にとって居心地がいいものがいい。
だからこそ、焦って選ばない。
無理に手にしない。
それが、わたしにとっての“選ぶ自由”の使い方。
一番むずかしかったのは、人との関わり
選ぶことには、優しさと同じくらい勇気もいる。
とくに人間関係においては。
このまま関係を続けていたら、きっと私は壊れてしまう――
そう感じたとき、距離を取ったことがある。
潮時って、あると思う。
お互いにとって、ちょうどいい別れがある。
深く関わるには覚悟がいる。
だからこそ、深く関わらないという選択にも、やさしさが宿ることがある。
“選ばない”のではなく、“これ以上を求めない”という選び方もあると思う。
選ぶ自由が、わたしの感性を育ててくれる
何を持つかではなく、何を選んでここに置くか。
それを丁寧に決めていく暮らしは、
わたしの感性を少しずつ整えてくれている気がする。
- 音のある/ない時間
- 手間をかけるという選択
- 深く関わらないという知恵
- 「なくてもいい」を認める強さ
どれも、「わたしはこう在りたい」という静かな意思表明だった。
おわりに|“選ぶ”ということは、自分と仲良くなること
今、わたしは“自由に選ぶ”ことを大切にしている。
それは、流行や常識から離れることでもあるし、
自分の感性にちゃんと耳を傾けることでもある。
たくさん持つよりも、
ちゃんと選んだものと一緒にいるほうが、ずっと心地いい。
▶ この記事が届いてほしい人へ
- 持たない暮らしに興味がある人
- 人間関係に静かな違和感を抱えている人
- 「選ぶ」ということに疲れてしまっている人
- 自分の感性で、ちゃんと選びたいと思っている人
▷ 私の楽天ROOM|選んでよかったものたち